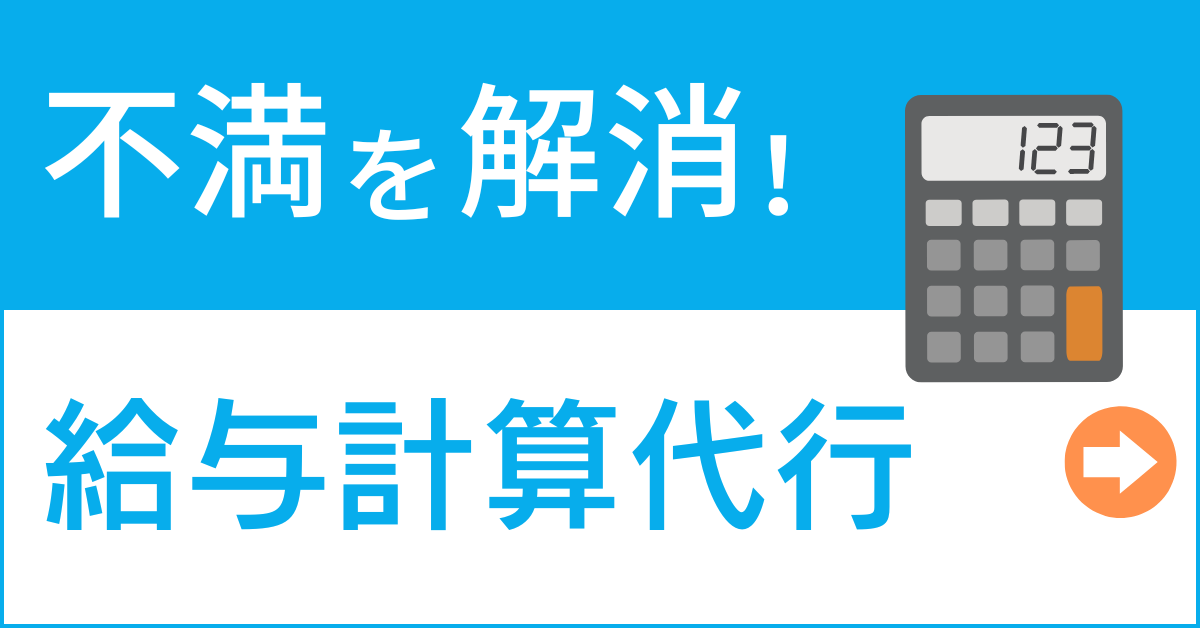控除とは、個人が納める税金を支給金額から差し引くことをいいます。
控除の種類はたくさんあるので知らない人の方が多いです。
控除の種類を理解しておくことで「いざ」というときに活用することができます。
今回は、控除とは?わかりやすく種類を解説!をご紹介します。
控除とは?
控除とは、個人が納めるべき税金を会社が支給した金額から差し引くことをいいます。
「天引き」ともいいます。
給与が社員の手元に届いたときには、すでに会社が国に税金や社会保険料を納めた金額になります。
また、あなたが会社で積み立てをしていて、貯蓄額や保険料の徴収を「給与天引き」にすると、「積み立て分」が差し引かれた金額が銀行に振り込まれます。
控除された金額は、給与明細で確認できます。
控除の種類
控除には多くの種類があり、人により受けられる控除が違います。
控除は大きく「2つ」に分けられます。
- (1) 所得控除
- (2) 税額控除
(1) 所得控除
個人の経済状況を税金の計算に反映させる制度です。
基礎控除
所得がある人だれでも受けられる控除です。
年収が低くても高くても受けることができます。
基礎控除額は一律38万円となっているため、その年の所得が38万円以下の人は基礎控除を引くことで所得が0になってしまうため、税金を払う必要がありません。
医療費控除
個人で負担した医療費分の控除が受けられます。
共通の家計費からの出費であれば、本人だけでなく家族の医療費も控除されます。
しかし年間で支払ったすべての医療費が対象となる訳ではなく、項目などによって変わってきます。
社会保険料控除
社会保険に加入している方であれば受けられる控除です。
配偶者を扶養に入れている場合などにも受けることができます。
社会保険料控除は「標準報酬月額×健康保険料」で計算されます。
そのため、個人事業主やフリーランスの方は「国民健康保険」になりますので、社会保険料控除は受けることができません。
雑損控除
資産が災害や被害に遭った場合、所得から差し引くことができます。
詐欺や恐喝の被害は対象になりませんのでご注意ください。
地震保険料控除
地震保険に保険料を支払った分の控除が受けられます。
控除は最高5万円までになります。
配偶者控除
所得が38万円以下の配偶者を扶養している場合に控除されます。
配偶者の年収や年齢によって受けられる控除額には差が生じます。
ただし、年収が1000万円以上の方には適用しません。
扶養控除
所得が38万円以下の子どもや親など、控除対象扶養親族がいる場合に受けられます。
生命保険料控除
生命保険や個人年金、介護医療の保険料を支払っている人が対象になる控除です。
障害者控除
自分もしくは配偶者、扶養家族が障がい者の場合に受けられます。
寡婦控除
12月31日の時点で判断され、「ひとり親」に該当しない人が27万円の所得控除を受けることができます。
ただし、再婚している場合は受けられません。
ひとり親控除
12月31日の時点で判断され、納税者がひとり親であるときに35万円の所得控除を受けることができます。
勤労学生控除
アルバイトしている学生が受けられる控除です。
控除は収入が130万円までの場合になります。
寄附金控除
国や地方公共団体や特定公益増進法人などに寄附金を払った人が受けられます。
「ふるさと納税」などが寄附金にあたります。
(2) 税額控除
控除額を直接所得税から差し引くことができる制度です。
住宅ローン控除
住宅ローンを組んでいる人が受けられます。
住宅ローンの控除を受けるには一定条件が必要になります。
配当控除
配当所得のある人が受けられます。
配当所得は、法人から得られる利益や利息の分配による所得のことです。
外国税額控除
外国所得税などがある人が受けることができます。
源泉徴収税額
源泉徴収とは、会社などが支払額から、本人にかわって国に納付する仕組みのことです。
すでに会社で天引きされているため、支払い済みの分を控除することができます。
災害減免額
自然災害で住宅や家財に損害があった場合に受けられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、控除とは?わかりやすく種類を解説!しました。
控除の種類を知っていれば、「いざ」というときに、この場合は○○という控除を利用すれば、負担が軽減できると気づくことができます。
そのためにも控除の種類を簡単にでも把握しておきましょう。
給与計算が負担となってしまっている担当者様へ
「通常業務が重なっていて、給与計算を処理する余裕がない・・・」
「急に経理担当が退職してしまって、人が足りない・・・」
こんなお悩みを持たれている担当者の方も多いと思います。
給与計算は毎月行わなければならない業務の一つです。
- 従業員の回答ミス・修正作業
- 問い合わせの対応
など、担当者の負担はとても大きい業務です。
「誰かに丸投げできれば・・・」と考えたことはありませんか?
ロジックスサービスでは、
固定費:55,000円(税込)
+
処理料金:1,100円/名(税込)
↓
例)25名の場合
月額:計 82,500円(税込)
上記の料金で給与計算アウトソーシングを対応しております。
細かい処理が必要な給与計算業務。
アウトソーシングすることで、経理担当者の負担を解消しませんか?